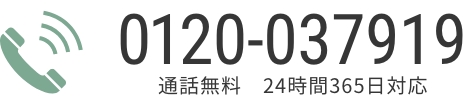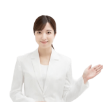お盆とは‐先祖を偲び、心をつなぐ大切な時間

一年に一度、ご先祖様がこの世に戻ってこられるとされるお盆。日々の忙しさの中で忘れがちな「つながり」を感じ、家族で穏やかに過ごす大切な機会です。この記事では、「お盆とは何か」「どう過ごすか」「どんな準備が必要か」基本から心構えまで、わかりやすくご紹介します。
お盆とは?
お盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が結びついた行事です。ご先祖様の霊がこの世に帰ってこられるとされる期間で、故人を供養し、感謝の気持ちを伝える時間とされています。
多くの地域では、8月13日〜16日の4日間を中心に行われます。
また新盆(しんぼん/にいぼん)とは、故人が亡くなってから四十九日を過ぎて初めて迎えるお盆のことを指します。
このお盆は特に手厚く供養する習わしがあり、ご遺族にとっても大切な節目となります。

お盆の過ごし方について
◆8月13日:迎え火
家の玄関先などで「迎え火」を焚き、ご先祖様をお迎えします。キュウリやナスで作った「精霊馬」を飾るご家庭もあります。
◆8月14~15日:供養やお墓参り
仏壇や精霊棚に果物や故人の好物などをお供えし、家族での語らいを通じて供養します。多くの方がこの期間にお墓参りをされます。
◆8月16日:送り火
ご先祖様が無事にあの世へ戻れるよう、灯りをともしてお送りします。京都の「五山の送り火」などが有名です。
新盆を迎える皆さまは一般的に以下の準備をします。※地域によって異なります
◆精霊棚(しょうりょうだな)の設置
仏壇とは別に、ご先祖様や故人を迎えるための供養棚を設けます。
・位牌・遺影・お花
・季節の果物・故人の好物
・水・お線香・ろうそく
・キュウリやナスの精霊馬
◆白提灯(新盆用提灯)
新盆では、「白張り提灯」を飾るのが習わしです。
ご先祖様が道に迷わず帰ってこられるようにと、玄関先や仏壇の前に吊るしたり、灯したりします。
※この白提灯は、新盆のときにのみ使い、基本的にはその年限りでお焚き上げに出します。
※但し、地域によっては白提灯を飾らないところもございます。
◆僧侶への依頼(読経)
新盆にあたって、寺院の僧侶を自宅にお招きし、読経をいただくこともあります。早めの僧侶の予約が必要です。
尚、お布施、御膳料なども併せて準備しましょう。
◆親族や近しい方への案内
新盆供養にあたって、親族や故人に縁のあった方へ案内を出すこともあります。
形式的な招待状でなくても、電話やはがきなどで日程を伝え、お参りや供養の意志を伝えましょう。
7月盆と8月盆と分かれている理由は?
お盆の時期が地域によって違うのは、昔の暦(旧暦)から今の暦(新暦)に変わったことと、それぞれの地域の生活の違いが関係しています。
明治5年(1872年)、日本では西洋のやり方を取り入れるために、旧暦(太陰太陽暦)から新暦(グレゴリオ暦)へと暦を変えました。
旧暦の7月15日は、新暦では毎年8月中ごろになります。
しかし、政府は行事もすべて新暦で行うようにと決めたため、いくつかの地域ではそのまま新暦の7月15日をお盆の日にしたのです。
そのため、地域によってお盆が「7月」に行われるところと「8月」に行われるところがあるのです。

お盆の宗派ごとの違いについて
北海道は浄土真宗のご家庭が多い地域です。
浄土真宗では、お盆に「ご先祖様の霊が帰ってくる」といった考え方は、もともとの教えには含まれていません。これは仏教の経典というよりも、日本に古くからある民間の信仰がもとになっているとされています。ですので、浄土真宗では精霊迎えや迎え火・送り火といった伝統的なお盆の行事を、宗教的な意味合いで行うことはあまりありません。
ただ、それでもご先祖様や亡くなった大切な方を偲ぶ気持ちは、どの宗派であっても自然なものです。そのため、浄土真宗のご家庭でも、お盆の時期にお仏壇をきれいに整えたり、故人を静かに思い出す時間を持つことはよくあります。
大切なのは、宗派や形式にとらわれすぎず、故人やご先祖様への感謝の気持ちを忘れずに過ごすこと。そうした心のこもったお盆の過ごし方は、とても意味深く、尊いものだと言えるでしょう。
お盆の準備リスト
お盆を迎えるために必要な準備を、分かりやすくまとめます。
お寺の考え方、地域や家のしきたりによって多少違いはありますが、一般的なリストです。
1. お盆飾り・祭壇関連
・盆提灯
・精霊棚(盆棚、しょうりょうだな)
・まこも
・蓮の葉
・精霊馬(キュウリやナスで作る馬や牛)
・ほおずき
・麻がら、迎え火・送り火用品【おがら、焙烙(ほうろく)皿 など】
2. 供え物
・果物(季節のもの、お好みのもの)
・野菜
・お菓子
・そうめん
・故人が好きだった食べ物
・水
3. 仏具・仏壇まわり
・お線香
・ロウソク
・花(生花)
・精進料理
・位牌・ご本尊の準備やお掃除
4. お墓参り用品
・掃除道具(ほうき、ちりとり、雑巾など)
・供花・線香・ろうそく
5. その他
・家族・親族帰省の連絡
・必要な食材や日持ちするお供え物の購入
まとめ
お盆とは、ご先祖様の霊を迎え、供養する日本の伝統行事です。
期間中に行われる送り火やお墓参り、盆踊りなどの風習には、長い歴史と深い想いが込められています。こうした慣習の意味を正しく理解し、地域や家族のしきたりに合わせて過ごすことが大切です。
たとえ年に一度であっても、ご先祖様とのつながりに思いをはせる時間は、忙しい現代社会において心の安らぎや家族の絆を深めるきっかけとなります。
ご先祖様を想う気持ちを大切にしながら、お盆の伝統や風習を次の世代へと受け継いでいきましょう。
関連記事
-
 お彼岸
お彼岸2025.03.14 春のお彼岸について
一年に一度、ご先祖様がこの世に戻ってこられるとされるお盆。日々の忙しさの中で忘れがちな「つながり」を感じ、家族で穏やかに過ごす大切な機会です。この記事で…
- 詳しく見る
-
 参列
参列2025.11.24 葬儀参列マナー完全ガイド|受付・挨拶・立ち振る舞い・携帯電話・持ち物まで徹底解説
一年に一度、ご先祖様がこの世に戻ってこられるとされるお盆。日々の忙しさの中で忘れがちな「つながり」を感じ、家族で穏やかに過ごす大切な機会です。この記事で…
- 詳しく見る
-
 お彼岸
お彼岸2025.08.21 秋のお彼岸とは?2025年の日程と過ごし方、北海道の風習もご紹介
一年に一度、ご先祖様がこの世に戻ってこられるとされるお盆。日々の忙しさの中で忘れがちな「つながり」を感じ、家族で穏やかに過ごす大切な機会です。この記事で…
- 詳しく見る