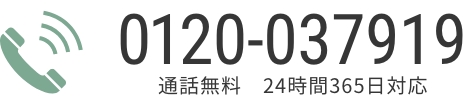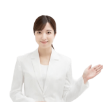秋のお彼岸とは?2025年の日程と過ごし方、北海道の風習もご紹介

お彼岸は、春と秋の年2回訪れる仏教行事で、ご先祖さまを供養する期間です。
仏教では、私たちが生きる世界を「此岸(しがん)」、悟りの世界・ご先祖さまがいる世界を「彼岸(ひがん)」と呼びます。春分・秋分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈むため、「此岸」と「彼岸」が最も近づく日とされ、この特別な時期に供養を行う習慣が根づきました。この期間は、単にご先祖さまを偲ぶだけでなく、煩悩を捨て、心を清め、自分自身を見つめ直す機会でもあります。
2025年秋のお彼岸の日程
2025年秋のお彼岸は、9月20日(土)から9月26日(金)まです。
秋分の日が9月23日(火・祝)で、その前後3日間が秋のお彼岸の期間となります。
・彼岸入り:9月20日(土)
・彼岸中日:9月23日(火・祝)
・彼岸明け:9月26日(金)

春と秋のお彼岸の違いは?
春のお彼岸と秋のお彼岸は、どちらもご先祖様を供養する仏教行事ですが、いくつかの違いがあります。
<期間>
●春のお彼岸: 春分の日を「中日」として、その前後3日間を合わせた7日間です。
●秋のお彼岸: 秋分の日を「中日」として、その前後3日間を合わせた7日間です。
春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日で、昼と夜の長さがほぼ同じになります。仏教では、極楽浄土は西方にあるとされているため、太陽が極楽浄土の方向へ沈むこの時期は、ご先祖様を供養するのに最も適した時期と考えられています。
<意味合い>
●春のお彼岸: 暖かくなって新しい生命が芽吹く季節に行われるため、自然をたたえ、生物をいつくしむという意味合いも含まれます。
●秋のお彼岸: 実りの季節に行われるため、収穫に感謝し、自然の恵みを分かち合うという意味合いも含まれます。
<お供え物>
●春のお彼岸: 「ぼたもち」をお供えします。春に咲く「牡丹(ぼたん)」の花にちなんでいます。
●秋のお彼岸: 「おはぎ」をお供えします。秋に咲く「萩(はぎ)」の花にちなんでいます。呼び方は違いますが、どちらもあんこで包んだ和菓子で、同じ食べ物です。また、旬の食材を使った精進料理をお供えすることもあります。春はタラの芽やたけのこ、秋はキノコやナスなどが用いられます。

北海道ならではのお彼岸の風習
北海道では、本州とは異なる独自のお彼岸の風習が根付いています。
<雪囲い>
秋のお彼岸の時期にお墓参りをして、冬に備えた「雪囲い」をする家庭があります。厳しい冬を前に、お墓を守る大切な準備です。雪の影響を考慮し、冬の前に墓地の整理や掃除を兼ねてお参りする意味合いが強く残る地域もあります。
<お供え物>
北海道では「赤飯」や「ぼたもち」などもよく供えられます。特に北海道の赤飯は甘納豆を使うのが特徴で、本州の小豆赤飯とは違った独自の文化が見られます。北海道でお彼岸に甘納豆の赤飯を食べる由来は、小豆の代わりに保存性の高い甘納豆を使ったことに始まります。砂糖が貴重だった時代、甘納豆入りの赤飯は特別なごちそうとされ、祝いの席や供養の場に広まりました。赤い色は魔除けを意味し、甘さには感謝の心が込められています。いまでは北海道ならではのお彼岸の習慣として定着しています。
<お墓参りの前倒し>
北海道は9月中旬でも冷え込みが厳しいため、天候の良い日に早めにお墓参りを済ませる家庭も多いです。車移動が前提の地域も多く、墓参りが家族のちょっとした行事や外出の機会にもなっています。
まとめ
秋のお彼岸は、お墓参りや仏壇へのお供えを通じて感謝の気持ちを伝えるとともに、心静かに自分自身を見つめ直す時間にもなりえます。また地域によっては、雪囲いや甘納豆の赤飯といった独自の風習も受け継がれています。それぞれの土地ならではの習慣を大切にしながらこの時期、ご先祖さまと心を通わせるひとときとして過ごしてみてはいかがでしょうか。
関連記事
-
 喪中寒中見舞い
喪中寒中見舞い2026.01.07 寒中見舞いとは?相手・自分が喪中の場合の意味や時期、失礼にならない書き方を解説
お彼岸は、春と秋の年2回訪れる仏教行事で、ご先祖さまを供養する期間です。仏教では、私たちが生きる世界を「此岸(しがん)」、悟りの世界・ご先祖さまがいる世…
- 詳しく見る
-
 葬儀社選び
葬儀社選び2025.04.22 葬儀社選びの重要性について
お彼岸は、春と秋の年2回訪れる仏教行事で、ご先祖さまを供養する期間です。仏教では、私たちが生きる世界を「此岸(しがん)」、悟りの世界・ご先祖さまがいる世…
- 詳しく見る
-
 お彼岸
お彼岸2025.03.14 春のお彼岸について
お彼岸は、春と秋の年2回訪れる仏教行事で、ご先祖さまを供養する期間です。仏教では、私たちが生きる世界を「此岸(しがん)」、悟りの世界・ご先祖さまがいる世…
- 詳しく見る