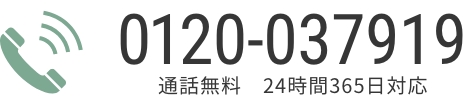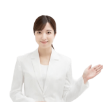葬儀の焼香マナー完全ガイド|宗派別のやり方と回数を徹底解説
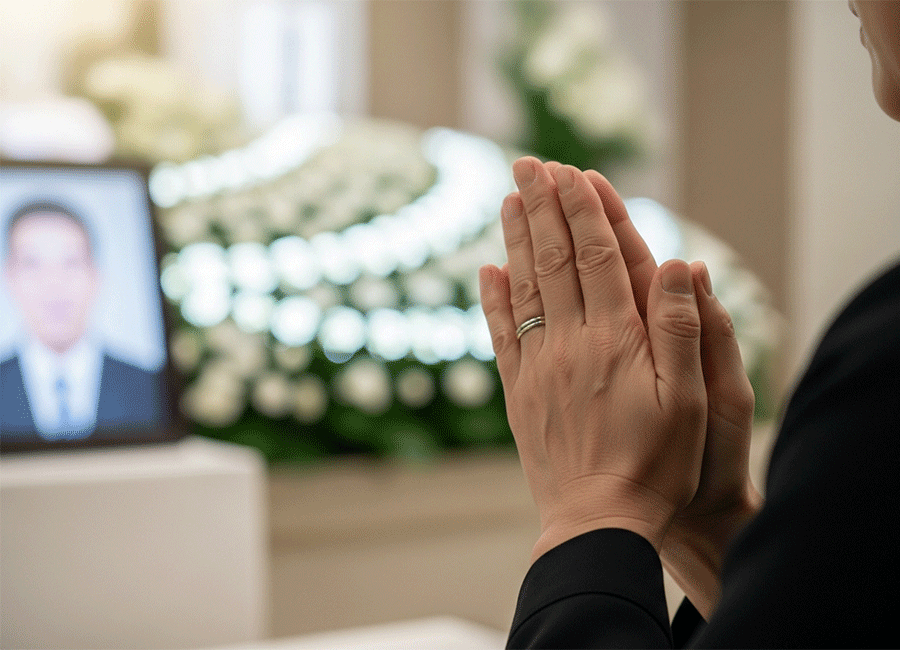
葬儀での焼香は、故人様への最後の別れと冥福を祈る大切な儀式ですが、作法に不安を感じる方も多いでしょう。大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない作法でさらに不安を感じる必要はありません。
こちらでは、作法の不安を解消し、故人様への敬意を込めて心穏やかに焼香ができるよう、分かりやすく解説していきます。
焼香の起源と仏教における香の意味
焼香の歴史は古く、仏教が日本に伝来するよりもはるか昔、古代インドにその起源を持つと言われています。当時、暑い気候の中で遺体の匂いを消すため、また病気の予防のために香が焚かれていました。それが仏教に取り入れられ、供養の際に香を焚く習慣へと発展していきました。
仏教において「香」は、その清らかな香りで心身を浄化し、邪気を払うものと考えられています。また、香は「仏様の食べ物」とも表現され、故人様や仏様への供養、感謝の気持ちを表す大切な道具とされてきました。
そして私たちが焼香をするのは、主に次のような意味も込められています。
1.故人や仏様への敬意と供養:香を焚くことで、故人様への哀悼の意と、仏様への感謝の気持ちを表します。
2.心身の浄化:香の煙には、私たちの心や身体、そしてその場の空気を清める力があると考えられています。心を落ち着かせ、故人様とのお別れに向き合うための空間をつくります。
3.故人様の冥福を祈る:香の煙が天へと昇るように、故人様の魂が安らかに浄土へ辿り着けるよう、祈りを捧げる行為でもあります。
このように、焼香は単なる形式ではなく、故人様を想い、自らを清め、冥福を祈るという、深い精神的な意味を持つ大切な儀式になります。

焼香の仕方には大きくわけて3つの作法があります。どんな宗派でも共通する基本的な焼香の流れを踏まえて説明します。
立って行う「立礼焼香」の作法
最も一般的なのがこの「立礼焼香」です。椅子席の斎場や、会葬者の多い大規模な葬儀でよく行われます。
・焼香台へ進む: 順番が来たら、案内係の指示に従って静かに焼香台へ進みます。歩く際は、数珠を左手に持ち、合掌したまま、ゆっくりと進みます。
・ご遺族・僧侶・ご本尊へ一礼: 焼香台の手前で、まずご遺族に一礼(軽く会釈程度)。次に、ご本尊(または故人様の位牌・遺影)に向かって一礼します。
・抹香をくべる: 香炉の前に進み、右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香(粉末状のお香)をつまみます。宗派によって異なりますが、額にいただく(目の高さまで持ち上げる)場合と、そのまま香炉にくべる場合があります。回数も宗派によって異なりますが、通常1〜3回です。
・合掌: 抹香をくべ終えたら、合掌し、心の中で故人様の冥福を祈ります。
・退場: 一歩下がってご本尊に一礼し、ご遺族にもう一度軽く一礼してから、静かに自分の席に戻ります。
座って行う「座礼焼香」の作法
座礼焼香は、畳敷きの会場などで正座のまま行う焼香です。
・焼香台へ進む:順番が来たら、静かに焼香台の前まで進みます。正座したまま前に進む場合と、立ち上がって進む場合があります。案内係の指示に従いましょう。
・ご遺族・僧侶・ご本尊へ一礼:焼香台の前で、まずご遺族に一礼(軽い会釈程度)。次に、ご本尊(または故人様の位牌・遺影)に向かって一礼します。
・抹香をくべる:香炉の前に正座し、右手の親指・人差し指・中指の三本で抹香をつまみます。宗派によっては、額にいただいてから香炉にくべる場合と、そのまま香炉にくべる場合があります。回数は1〜3回が一般的です。
・合掌:抹香をくべ終えたら、両手を合わせて合掌し、心の中で故人様の冥福を祈ります。
・退場:一礼したのち、静かに元の席へ戻ります。歩く際や正座の立ち座りの動作は、音を立てず丁寧に行いましょう。
複数人で回す「回し焼香」の作法
会葬者が多い場合や、スペースが限られている場合に「回し焼香」が行われることがあります。これは、香炉と抹香が参列者の間を回ってくる形式です。
・回ってきた香炉を受ける: 自分の番が来たら、次の人へ回す前に、軽く会釈して受け取ります。香炉は膝の上ではなく、自分の前の床に置くのがマナーです。
・抹香をくべる: 抹香盆を自分の前に置き、立焼香や座焼香と同様に抹香をつまみ、香炉にくべます。
・合掌: 焼香が終わったら、合掌し、故人様のご冥福を祈ります。
・次の人へ回す: 合掌を終えたら、香炉と抹香盆を次の参列者の方へ回します。その際も、軽く会釈をするのが丁寧です。香炉を落とさないよう、ゆっくりと渡しましょう。
どの種類の焼香でも、大切なのは故人様を想う気持ちです。形式を完璧にこなすことよりも、心を込めて丁寧に行う姿勢が何よりも尊いことだということが大事になります。
【宗派別】焼香の回数と作法の違い
基本的に、参列者は故人様やご遺族の宗派に合わせるのが丁寧とされていますが、もし宗派が分からない場合は、無理に合わせる必要はありません。心を込めて1回焼香すれば、失礼には当たらないとされているのでご安心下さい。
ここでは、主要な宗派における焼香の回数と作法の違いをまとめました。

天台宗の焼香
天台宗では、回数に厳密な決まりはなく、1回または3回とされています。抹香を額にいただく作法が一般的です。
真言宗の焼香
真言宗では、3回焼香するのが基本とされています。抹香は額にいただきます。
浄土宗の焼香
浄土宗では、回数に明確な決まりはありませんが、1回から3回行うのが一般的です。
浄土真宗の焼香
浄土真宗は、他の宗派と焼香の意味合いが大きく異なります。故人様を「往生即成仏」として捉え、自らの行いによって故人様が成仏するのではなく、阿弥陀如来の力によって救われるという考え方です。焼香は本願寺派(お西)は1回のみで、抹香を額にいただかず、また真宗大谷派(お東)の焼香は2回で、抹香を額にいただくことはありません。
臨済宗の焼香
臨済宗では基本的に1回焼香し、抹香は額にいただきません。「香」をくべることで自身の心を清めるという意味合いを持ちます。
曹洞宗の焼香
曹洞宗では、2回焼香するのが正式な作法です。1回目は故人様への供養、2回目は自己の心身を清めるという意味があります。1回目は額にいただきますが、2回目はそのまま香炉にくべます。
日蓮宗の焼香
日蓮宗では、3回焼香するのが基本です。抹香は額にいただきます。
このように、宗派によって違いがあるのが焼香です。もし、故人様やご遺族の宗派が分からなくても、前の方の作法に倣う、あるいは心を込めて1回焼香すれば、まず問題ありませんのでご安心ください。
まとめ
北海道では通夜の回し焼香、葬儀・告別式は出焼香が一般的でしたが、近年は家族葬の増加や参列者への配慮から、葬儀・告別式でも回し焼香が行われることが増えています。
焼香は、故人様への追悼とともに自らの心を清める大切な儀式です。立礼焼香・座礼焼香・回し焼香と形式はさまざまですが、最も大切なのは「故人を想う気持ち」を込めて丁寧に行うことです。
形式にとらわれず、静かに心を整えて香を手向けることが、何よりの供養となるでしょう。
関連記事
-
 参列
参列2025.11.24 葬儀参列マナー完全ガイド|受付・挨拶・立ち振る舞い・携帯電話・持ち物まで徹底解説
葬儀での焼香は、故人様への最後の別れと冥福を祈る大切な儀式ですが、作法に不安を感じる方も多いでしょう。大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない作法でさ…
- 詳しく見る
-
 葬儀社選び
葬儀社選び2025.04.22 葬儀社選びの重要性について
葬儀での焼香は、故人様への最後の別れと冥福を祈る大切な儀式ですが、作法に不安を感じる方も多いでしょう。大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない作法でさ…
- 詳しく見る
-
 香典
香典2025.09.24 香典の基本マナー完全ガイド|袋の書き方・表書き・渡し方
葬儀での焼香は、故人様への最後の別れと冥福を祈る大切な儀式ですが、作法に不安を感じる方も多いでしょう。大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない作法でさ…
- 詳しく見る